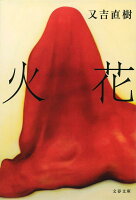第153回芥川賞受賞作。純文学としての「火花」をどのように読み解いていくのか。芥川賞受賞作を読むたびに、自分自身の純文学の読解力のなさに辟易してしまいます。「火花」においても、純文学として何が評価されたのか理解できませんでした。人の心象を深く抉っているのでしょうか。私は読み取れませんでした。
「火花」は、評価する人と批判する人がはっきり分かれているような気がします。作者が人気お笑い芸人ということで、作品の評価にバイアスがかかっているのでしょう。作品の評価より先に受賞者が現役芸人「又吉」だということの話題が先行し、作品の評価に影響を与えているのは間違いありません。
「火花」の内容
売れない芸人の徳永は、天才肌の先輩芸人・神谷と出会い、師と仰ぐ。神谷の伝記を書くことを乞われ、共に過ごす時間が増えるが、やがて二人は別の道を歩むことになる。笑いとは何か、人間とは何かを描ききったデビュー小説。【引用:「BOOK」データベース】
「火花」の感想
芸人ネタが多い
売れない先輩芸人「神谷」を後輩「徳永」の視点で描いています。徳永が一瞬で心酔するほど、神谷の笑いに対する姿勢とセンスには秀逸なものがあるということでしょうか。その割には、二人のやり取りには面白いものを感じない。会話にしてもメールにしても全く笑えない。メールのやり取りの時の差出人の名前のどこに笑える要素があるのか理解しがたい。
「現実的な返答をしてしまい申し訳ございませんでした。 カノン進行のお経」
「聞こえていなかったと信じて明日から生きていこうと思ってたのに。 三畳一間に詰め込まれた救世主」【抜粋】
「あほんだらさん、面白かったです。 彼女と瓜二つの排水溝」
「十位のお前に聞くことちゃうんやろうけど。 エジソンが発明したのは闇」【抜粋】
二人のメールのやり取りですが、ここは笑うところなのでしょうか。この面白さが分からない私は笑いの感性がないのかな。深刻とまではいかないけど、真剣な内容のメールに敢えてくだらない笑いを入れてしまう売れない芸人の性(さが)を表現したかったのかな、と好意的に解釈していますが。
作中の随所に芸人同士の決まり事みたいなものを書き、いかにも芸人とはかくあるべきだと宣言している感もあります。それが妥当なことなのかどうかは別にして、芸人はこうなのだと押し付けられている気がします。例えば、
- 先輩に誘われれば、どんなに重要な用事があっても顔を出す
- 先輩は、お金があってもなくても必ず奢る
- 飲む時は、徹底的に飲む。
などなど。これらは一般社会においても多少はあることですが、芸人の世界では徹底しているということでしょう。これらを、いかにも芸人自慢のように延々と書き続けられていく。だんだんと飽きてきます。
笑いをどこに求めるのか
神谷は、自らが信じている笑いを追求し続けていきます。それらが世間に受け入れられるかどうかは問題ではないようです。自分が面白いことは、世間も面白いと真剣に思っているのかもしれません。ただ、世間に受け入れられない笑いを押し通し続けることは芸人としてどうなのかということです。そのことについては、神谷の才能に心酔している徳永も次第についていけないと気持ちが変化していってます。
そもそも芸人とは、一体何なのか。
職業として、人(客)を笑わせることが芸人だと思うのです。自分自身の笑いにどれほどの信念があろうとも、客が笑わなければ職業としての芸人では有り得ない。大衆迎合と言われるかもしれませんが、それがお笑い芸人の本質だと思います。笑わすのか、笑われるのかは重要な問題ではないと思います。結果として、客が笑うのかどうか。それだけが重要なことだと思います。そこに気付かない神谷は、面白くない上に鈍感な人間に感じます。徳永も、客を笑わせるために努力をしています。自分の信じている笑いではないとしても、芸人としては正しい道でしょう。神谷の笑いに対する姿勢は、私には許容できない。
最後に
結局、神谷は売れずじまい。徳永も多少売れたが、相方の引退により自らも引退を決めます。結局10年間の二人の軌跡の中で神谷は何も変わらず、変化を遂げてきたのは徳永の方です。徳永の変化する心象が、純文学なのかな。神谷は、笑いに固執する単なる売れない芸人にしか感じませんでした。徹底した笑いへの固執でしたが。
私は賞レースにあまり興味はないですが、芥川賞か直木賞かと聞かれれば、直木賞受賞作の方が読んでいて楽しいと感じます。本屋大賞も同様です。分かりやすく楽しめる小説が好みだからです。「火花」は、芸人の話の割には笑えなかったです。
映像化について
ドラマ・映画と映像化されています。舞台も上演されるようです。ドラマも映画も観ていないので、何とも言えませんが、映像で観ると面白いのかもしれません。