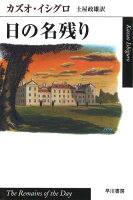カズオ・イシグロ氏が、ノーベル賞を受賞したので読みました。恥ずかしながら、そういうことです。おそらくノーベル賞がなければ、読む機会はなかったと思います。
文章がとても美しい。と言っても原文は英語なので、日本語訳が素晴らしいということになるかもしれません。ただ、原文が素晴らしいからこそ、日本語訳も素晴らしいものになったのだと思います。もちろん、訳者の土屋政雄氏の力量も大きいのは間違いありません。もうひとつ感じたのは、「イシグロ氏は、英国人なんだな」と言うことです。この小説を読むと、彼のアイデンティティは英国にあると感じざるを得ません。彼の経歴から言えば、それは不思議なことではありませんが。
「日の名残り」の内容
品格ある執事の道を追求し続けてきたスティーブンスは、短い旅に出た。美しい田園風景の道すがら様々な思い出がよぎる。長年仕えたダーリントン卿への敬慕、執事の鑑だった亡父、女中頭への淡い想い、二つの大戦の間に邸内で催された重要な外交会議の数々―過ぎ去りし思い出は、輝きを増して胸のなかで生き続ける。【引用「BOOK」データベース】
「日の名残り」の感想
世界大戦
舞台は、第二次世界大戦後のイギリスです。しかし、語られる内容のほとんどは第一次世界大戦後から第二次世界大戦前のイギリスです。その時代を、ダーリントン卿の執事として働いた「スティーブンス」の回想が物語の中心です。回想なので、確かな記憶でない部分も多くあります。そのことについては、スティーブンス自身が確実な記憶でない、と語っています。
理想の執事
一流の執事として働いてきたと自負するスティーブンスの回想なので、言葉遣いが執事らしく丁寧で美しい。イギリスにおける執事と言う職業が、どのようなものなのか。それを正確に知っている訳ではないので、スティーブンスの行動が執事の理想なのかどうかは分かりません。ただ、彼はそれを求め続けたのは間違いない。そのことが彼の人生を充実したものにしたのか、そうでないのか。
彼が人生に求めるものは一流の執事であること。そして、一流の執事に必要なものは「品格」だと考えています。この「品格」の考え方が、おそらくイギリス人としての考え方を元に描かれています。それも古い時代のイギリスの考え方。この考え方に縛られてスティーブンスが過ごした人生が、彼にとって最善だったのか。スティーブンスは、回想とともに考えます。
過去を振り返る
彼の人生に最も影響を及ぼしたのが、雇主である「ダーリントン卿」と女中頭であった「ミス・ケントン」です。彼らに対しスティーブンスが取り続けた態度は、正しかったのか。執事として。一人の人間として。
過去を振り返り続けた旅で、スティーブンスが気付いたこと。それは、取り返しのつかない過ちを犯していたのかもしれないということです。ダーリントン卿のことも、ミス・ケントンのことも。旅の最後に、ある男が、過去に囚われたスティーブンスに語りかけます。
「夕方が一日でいちばんいい時間だ」
今のスティーブンスの年齢からでも、過去に囚われず未来を見つめ生きていくことが出来る。そのことに気付かせてくれるのです。
終わりに
美しい文章と描写で描かれた一人の執事の物語が、人生の本質を描いているのかもしれません。
初めて読んだカズオ・イシグロ氏の小説で感じたことは美しいということです。文章ももちろんですが、扱う人間の本質が美しいということです。当時のイギリス人とは、こういうものだったのか。それとも、一部の特権階級の話なのか。そのあたりは分かりませんが、少なくとも、かつてイギリスにあった精神的な支柱だったに違いありません。